- 多嚢胞性卵巣症候群と診断された方
- 流産を経験した方
- 流産の予防法を知りたい方
多嚢胞だと流産しやすいって
聞いたけど本当?
こんにちは!
不妊治療中の20代後半夫婦です!
僕たち夫婦は2回の流産を経験しました。
どちらも妊娠5週の出来事です。

多嚢胞だと卵子の質が悪いみたい
だから2回連続で流産したのかもしれない
妻はそんな不安を吐露してくれました。
今回はそんな妻の不安を解消するために
多嚢胞と流産の関係、
卵子の質向上についてまとめました。
多嚢胞性卵巣症候群
多嚢胞性卵巣症候群は
SNSなどではpcosと
記載されることもあります。
妻も多嚢胞性卵巣症候群と診断されています。
多嚢胞性卵巣症候群とは
- 卵巣にたくさんの小さな卵胞(卵の袋)ができる状態。
- 卵胞が育ちにくく、排卵がうまく起こらないことが多い。
- ホルモンのバランス異常が関係していると考えられている。
主な特徴
- 月経不順(生理周期が長い・不規則)
- 排卵しにくい、不妊の原因になることがある
- 男性ホルモンの影響による症状(にきび、多毛など)
- 超音波検査で「ネックレスサイン」と呼ばれる卵胞の並びが見られる
個人差がありますが排卵が起きづらく、
月経不順になることが大きな特徴です。
妻も低用量ピルを服用しなければ
半年月経が起きません。
さらに僕がパートナーとして感じる
多嚢胞の特徴は
突然感情の起伏が激しくなること。
男性ホルモンと女性ホルモンのバランスが悪く、イライラが出やすいようです。
かわいそうだ、、、、
しかも月経前症候群:PMSとは違い、
排卵が時期でなくてもイライラが起き、
イライラする時期が読みにくい辛さもあります。
僕と妻の闘いはこちらの記事で!
多嚢胞と流産

- 流産確率は通常より高い傾向にある
- 通常10-15%に対し、20-30%というデータも
- 対策すれば通常と変わらなくなる
- 不妊治療している場合はホルモン拡充や良質な受精卵の移植が行われるため、多嚢胞と流産にはほとんど関係がないと考えられる
多嚢胞と流産の関係を調べてみると
確かに通常より流産確率が高いというデータあるようです。
ホルモンバランスの乱れが大きく
着床や流産に影響があるみたい。
例えば子宮内膜が十分なほど厚くならなかったり、子宮内環境が良くないことで着床しづらいことがあげられます。
とはいえ、必ず流産するということはなく、
大きく関係しないとの見方をしているクリニックもあります。
流産は、必ずしも夫婦側に原因があるものとは限りません。流産で最も多い原因は「胎児の染色体数の異常」であり、これは両親の染色体が正常だとしても起こりうることです。そのため、健常な夫婦でも1回の妊娠に対する流産率は10%以上あるといわれます。
多嚢胞が原因で流産しているのではない可能性もあります。
通常でも10%以上流産の確率があることは理解しておきましょう。
<参考リンク>
多嚢胞性卵巣症候群高流産率の原因及び予防 | 文献情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター
ではどうして多嚢胞だと流産が起きやすいと言われているのでしょうか。
考えられる要因
ホルモンのアンバランス
- 排卵は起きても、黄体ホルモン(プロゲステロン)が十分に出ないことがあり、
子宮内膜がうまく育たず、受精卵を維持できない → 初期流産につながりやすい。
インスリン抵抗性
- PCOSの方に多い代謝異常。インスリン抵抗性は子宮環境や卵の質に悪影響を与え、流産率を高める可能性が指摘されています。
肥満との関連
- PCOSでは肥満を合併する人が多く、肥満は流産リスクを上げる因子の一つ。
卵子の質への影響
- ホルモンバランスや代謝の乱れで卵子の成熟に影響が出ることがあり、受精や着床後の発育に影響する可能性。
ホルモンのアンバランスにより
「子宮内膜が十分育たない」、「肥満」、
「卵子の未成熟」などに
影響する可能性があるようです。
しかし対策すれば、
多嚢胞でない人と変わらないくらいに
確率を抑えることができると言われています。
対策・予防のアプローチ
- 生活習慣の改善(体重管理・血糖コントロール)
- 薬物療法
- インスリン抵抗性が強い場合 → メトホルミンが有効なことがある
- 黄体ホルモン補充で妊娠初期をサポートする場合も
- 高度生殖医療(ART)
- 卵巣刺激や胚移植で妊娠率・出産率を高められるケースもある
僕たちの場合は、
ARTにより対策されていたことになります。
- 凍結胚移植で妊娠判定
- 移植前からホルモン剤で子宮内膜の厚みUP
- 移植後も薬でホルモンの均衡を保っている
多嚢胞の妊娠のしづらさは
前述の通り、卵子の質の悪さも一因です。
しかし体外授精であれば
胚まで育った質のよい受精卵を
子宮に戻すことになります。
遺伝子不良までははじくことはできませんが、
成長の早い、良質な受精卵が残ることは確かです。
また子宮内膜の厚みや妊娠継続に必要なホルモンも薬剤で補うことができるため、
多嚢胞のデメリットをカバーすることができています。
妻の言う「多嚢胞のせいで卵子の質が悪く、2連続で流産したんじゃないか」という不安にはこれで答えが出たと思います。
今回の原因は多嚢胞ではなく、
胚盤胞の遺伝子不良で不運にも流産してしまったというのが正解でしょう。
しかし原因がそうだったからと言って
喜ばしいものでもありません。
流産なんて二度と経験したくありません。
流産をなるべく予防するにはどうすればよいのでしょうか?
多嚢胞(PCOS)における流産予防の考え方

1. ホルモンバランスを整える
- 黄体補充(プロゲステロン)
→ 胚移植周期や自然妊娠後に黄体ホルモンを補充し、子宮内膜を安定させる。 - ホルモン補充周期での移植
→ 凍結胚移植で外からエストロゲン・プロゲステロンを投与することで、PCOSによる排卵後の不安定さを回避。
2.インスリン抵抗性の改善
- メトホルミン(糖尿病治療薬)
→ PCOSの方にしばしば使われ、インスリン抵抗性改善だけでなく、流産率を下げる可能性も報告されています。 - 生活習慣改善
- 適正体重の維持(肥満は流産リスクを上げる)
- バランスの良い食事(低GI食など血糖コントロールを意識)
- 適度な運動
3. 血液凝固異常や免疫因子のチェック
- PCOSの方の中には、血液が固まりやすい「血栓傾向」や免疫異常が関与している場合も。
- 必要に応じて、アスピリン・ヘパリン療法が行われることがあります(不育症外来で検査・判断)。
4. その他のサポート
- サプリメント
- 葉酸(妊娠初期の必須サプリ)
- ビタミンDやミオイノシトールはPCOS女性の卵質改善・代謝改善に有用という研究もあり。
- ストレスケア
→ 自律神経の乱れやストレスホルモンも妊娠維持に影響するため、睡眠やリラクゼーションも大切。
PCOSによる流産リスクは
「ホルモン補充」「生活習慣改善」
「メトホルミン」などで軽減できる可能性があります。
また前述の通り不妊治療をしている方であれば、
基本的にはホルモン拡充により多嚢胞のデメリットを
打ち消せているため生活習慣改善やサプリでの栄養補充がメインの対策となります。
しかし流産の多くは
赤ちゃん側の染色体異常が原因で、
PCOSの方に限らず誰にでも
起こり得ることは頭に入れておきましょう。
「自分のせいではない」ことを理解しつつ、医師と相談して予防できる部分は取り入れていくことが大切です。
併せて流産をなるべく防ぐために
卵子の質をよくする手法もご紹介します。
PCOSで卵子の質を向上させるポイント

1. 体重・代謝の改善
- 適正体重を目指す
→ 体重の5〜10%減量で排卵率や卵子の質が改善する報告あり。 - 食事改善
- 低GI・低糖質を意識(血糖値の乱高下を防ぐ)
- 野菜・良質なたんぱく質・オメガ3脂肪酸を多く摂る
- 加工食品・糖分過多を控える
2. インスリン抵抗性の対策
- メトホルミン(医師の処方)
→ インスリン抵抗性を改善し、排卵や卵質に良い影響。 - ミオイノシトール(サプリ)
→ PCOS女性に広く使われており、排卵誘発・卵子の質改善のエビデンスが増えてきています。 - ビタミンD
→ 欠乏が多く、補充で卵巣機能の改善が期待できるケースも。
3. ホルモン環境を整える
- 不妊治療では、適切な排卵誘発方法を選ぶことが大切。
→ クロミッド、レトロゾール、注射など、PCOSに合った方法で卵胞を「成熟」させるサポートを行います。 - ホルモン補充周期で子宮環境を整えるのも有効。
4. 生活習慣の最適化
- 睡眠の質を上げる(ホルモンバランスは睡眠に強く左右される)
- 運動習慣(有酸素+軽い筋トレでインスリン感受性UP)
- 禁煙・控酒(酸化ストレスは卵子の質を下げる)
5. 抗酸化サポート
- PCOS女性は酸化ストレスが強いことが多いとされます。
- コエンザイムQ10
- ビタミンE、ビタミンC
- NAC(N-アセチルシステイン)
など抗酸化サプリが卵子の質改善に役立つという研究もあります。
卵子の質は「年齢」が最も大きな要因ですが、
PCOSでは「インスリン抵抗性」
「ホルモンの乱れ」「酸化ストレス」が
卵子の質を下げる原因になりやすいと言われています。
採卵を繰り返すことがあれば、意識して取り組むとよいでしょう。
生活習慣改善+サプリメント+必要に応じて薬物治療を組み合わせることで、
卵子の成熟や質の改善が期待できるでしょう。
<参考リンク>
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性におけるメトホルミンの使用:機会、利点、および臨床的課題 – Saadati – 2025 – 糖尿病、肥満、代謝 – Wileyオンラインライブラリ
IVF-ETを受けている肥満不妊PCOS患者における顆粒膜細胞における妊娠転帰、神経生殖代謝ホルモンおよび遺伝子発現プロファイルに対する減量の影響 – PMC
まとめ:流産が不安な方へ
今回は多嚢胞と流産について
関係性をまとめました。
多嚢胞性卵巣症候群は妊活においては不利な、10人に1人持っていると言われる体質です。
すぐに改善することはなかなか難しいかもしれません。
しかし体外授精においては、多数採卵ができ、大きなメリットだったりします。
妻も多嚢胞に苦しめられていますが、ポジティブに考えることが妊娠に一番近づけると考えて頑張っています。
体質を恨むことも多いかもしれませんが、うまく付き合っていきながら、一緒に不妊治療を継続していきましょう。
僕も妻と一緒に進めるようがんばります。
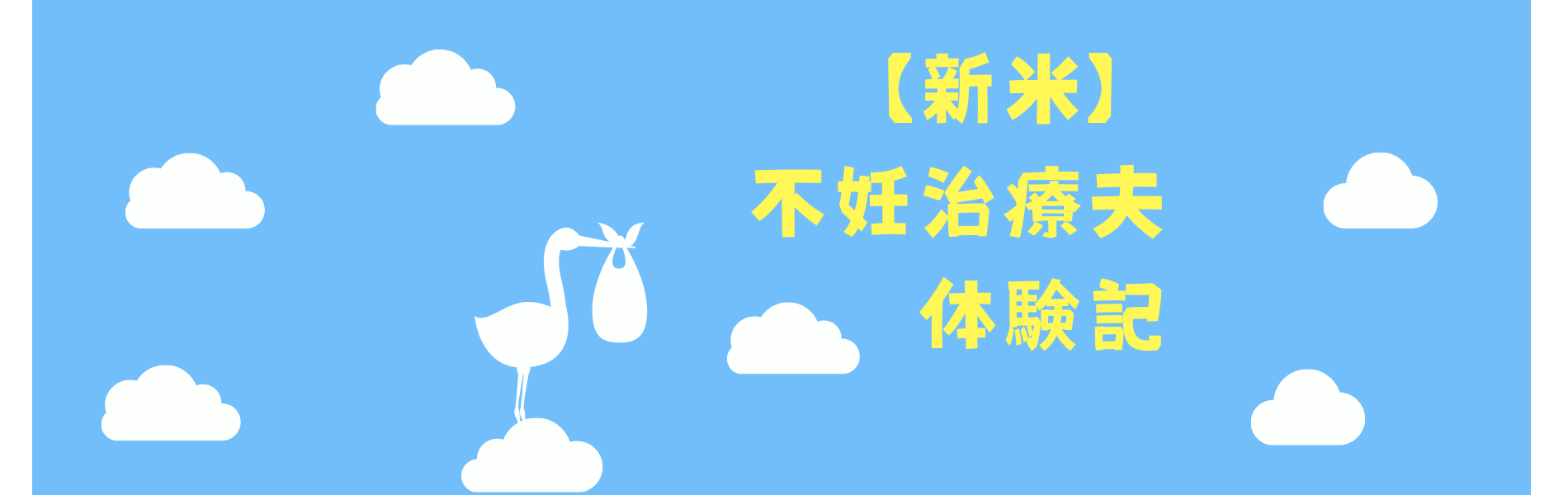
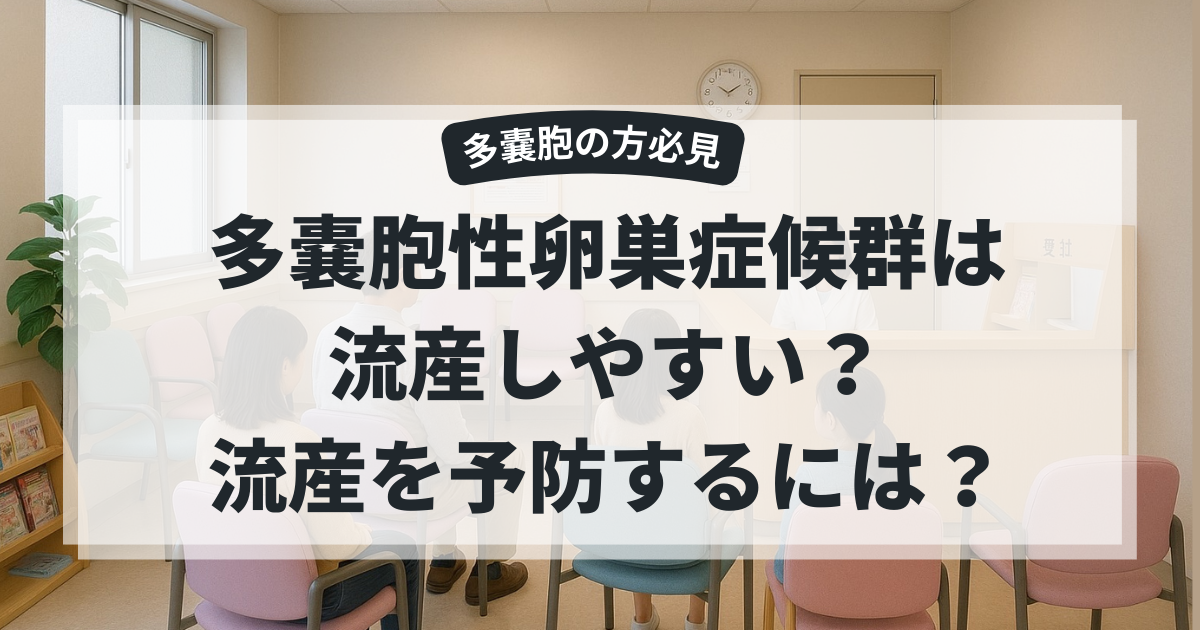

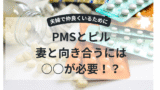
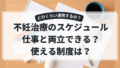
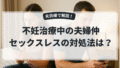
コメント